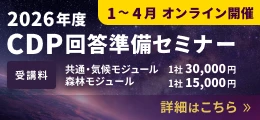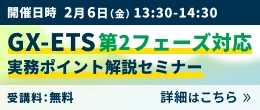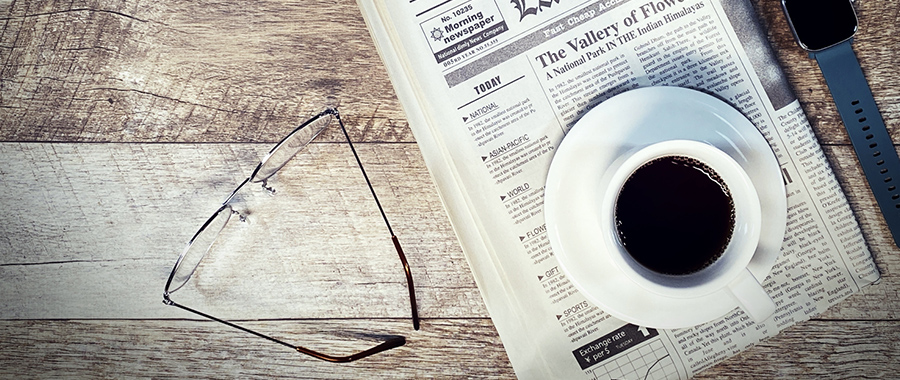サプライチェーンセキュリティの現状
自動車産業は CASE(Connected、Autonomous、Shared & Services、Electric)に代表される技術革新により、IT の活用が急速に進んでいます。
同時に、ネットワーク接続の拡大により、以下のサイバーセキュリティリスクが深刻化しています:
•社内環境へのインターネットからの攻撃
•関係企業や取引先のネットワークへの不正侵入
•企業間ネットワークを経由した攻撃
•サプライチェーンを狙ったサイバー攻撃
「JAMA・JAPIA自工会/部工会サイバーセキュリティガイドライン」においては、自動車産業に関係するすべての会社を想定しサイバーセキュリティ対策として、ガイドラインを示しています。
また、経済産業省は、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度構築に向けた中間取りまとめ」を公表しました。
経済産業省は、サプライチェーンにおける重要性を踏まえた上で満たすべき各企業のセキュリティ対策を提示しつつ、その対策状況を可視化する仕組みの構築に向けた検討を進め、現時点での検討の概要を「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度構築に向けた中間取りまとめ」として公表しました。
今後、2026年度の制度開始を目指し、実証事業や制度運営基盤の整備、利用促進に向けた各種施策の実行等を進めていく予定です。
ISMS認証のメリット
1. 体系的なセキュリティ管理体制の構築
ISMS認証を取得することで、組織内に情報セキュリティを体系的に管理する仕組みが構築されます。ガイドラインが示す「平時の情報セキュリティリスクを管理する体制」や「情報セキュリティ事件・事故発生時の対応体制」など、基本的な要素を整備することができます。
2. 業界標準への適合
JAMA・JAPIAのサイバーセキュリティガイドラインは、ISMS認証制度と相互補完的な制度として位置づけられています。ガイドラインにも記載されているように、「先行する自己評価の仕組みである「SECURITY ACTION」、「JAMA・JAPIA自工会/部工会サイバーセキュリティガイドライン」や国際標準である「ISMS認証制度」等とは相互補完的な制度」となっています。
3. 取引先からの信頼向上
ガイドラインの「サプライチェーン上で発生する情報セキュリティ要件が明確」になっていることが求められています。ISMS認証を取得することで、取引先に対して自社のセキュリティ管理体制を客観的に示すことができます。
4. リスクの体系的評価と対策
ガイドラインの「情報資産の機密区分を設定・把握し、その機密区分に応じて情報を管理していること」という要求事項にもあるように、ISMS認証プロセスでは情報資産を特定・分類し、リスク評価を行います。これにより、体系的なリスク管理が可能になります。
5. 相乗効果の創出
ISMS認証とJAMA・JAPIAガイドラインは互いに補完し合う関係にあります。ガイドラインに記載されているように、「具体的には、現在の★3、★4の要求項目案は「JAMA・JAPIA自工会/部工会サイバーセキュリティガイドライン」の内容とも整合性を一定程度確保しており、双方の取り組みを組み合わせることで、効率的かつ効果的なセキュリティ対策が可能になります。
まとめ
ISMS認証の取得は、組織のサイバーセキュリティ体制を強化するだけでなく、あらゆる業界のサプライチェーン全体のセキュリティ向上にも貢献します。ガイドラインの目的にあるように「日本の産業全体のサイバーセキュリティ対策のレベルアップや対策の効率的な点検を推進する」ためにも、ISMS認証取得をお勧めします。
執筆者
ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社
ヘッド・オブ・サーティフィケーション 朝井 光治